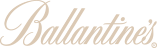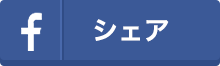18時に咲島はカウンター席に着いた。営業開始とほぼ同時であったから、客は自分ひとりであろうと思い込んでいたのだが、ひと組のカップルがすでにオーダーしようとしている。咲島はそのふたりから4席ほど空けて腰を落ち着けた。
「凄いね。いきなり、つづけざまに客とは」
小声でバーテンダーの柏原に驚きを伝えると、彼は「ありがたいことです。でも今夜はどうですかね」とちょっと渋い顔をした。昼前から崩れた天気のことを気にしているのだろう。2月のみぞれまじりの冷たい雨は、夜になって雪に変わるかもしれない。
「ああ、雪にならないといいな」
咲島はこう応えたが、今夜このヒルトン東京に泊まる自分にとっては天気などどうでもよかった。柏原はそれを察してか、「では、久しぶりに咲島さんにたっぷりと味わっていただきましょう」と言って笑顔になった。
シトラスでクールなジントニックを身体に馴染ませた咲島は、いつものようにウイスキーのストレートをオーダーした。柏原が「フレグランススタイルにいたしましょうか」と聞いてきたので、「あなたの期待に応えて、今夜はじっくりといくか」と言って咲島は頷いた。
小ぶりのワイングラスにバランタイン17年を注ぐと、柏原はアトマイザーのミニチュアボトルを手にして1プッシュ、グラスにスプレーした。するとカップルの女性客の声が小さく聴こえた。
「いまの何。カッコイイ」
女性は30歳前後か。男性はそれより少し年上だろう。柏原はその声に思わず微笑みながら、咲島に「どうぞ、ごゆっくり」とグラスをすすめた。そして女性のほうを向いて「カッコイイかどうかわかりませんが、香りをより華やかに堪能できますよ」と伝え、カップルの接客へと移っていった。
バランタイン17年の入ったアトマイザーをふたりに見せながら柏原が丁寧に説明をはじめるのを微笑ましく思いながら、咲島はグラスを鼻に近づけて香りを楽しんでみる。甘美さのなかに密やかなスモーキーさやバニラ香、潮の香などが浮遊してくる。ノージングしてゆったりと口に含む。美味とはいい表現だと実感する。上質な味わいには美があるのだ。
こんなに落ち着いてウイスキーを飲むのは久しぶりだった。帽子も被らず、サングラスも掛けず、素の姿で人前にいる自分も久しぶりだ。映画監督の咲島だとは誰も気づきはしない。
撮影現場はもちろん映画監督という立場で人前に出るときは、絶対に素顔を見せない。
監督として名が売れはじめた頃、興行的にいまひとつの作品があった。前評判は高かったのにもかかわらず、観客動員数は映画会社の予想を下回った。自分としては描ききったつもりで自信があっただけにショックだった。
あるパーティーの帰り、名高いベテラン女優の華杉愛に「わたしの家で飲まない」と誘われた。なんと彼女の家はヒルトン東京だった。「愛さんが長年ホテル住まいだと噂には聞いてはいましたが、ほんとうだったんですね」と咲島が言うと、「そんなに驚くことないわよ。でも、いまこのホテルが住まいだってことは内緒ね」と愛は答えながら、慣れた様子でセント・ジョージ バーに入っていった。
バーテンダーは客の前でカクテルをつくることをゆるされたばかりの柏原だった。愛はまだ若かった柏原を相手に飲むのを楽しんでいるようだった。
その席で、酔った愛に自分のひ弱さを指摘される。咲島とは親子ほどの年齢差がある女優は、「あなたはいい人で、演技者やスタッフの想いを尊重してくれるが、それが良さとも言えるけれど、わたしには弱点に映る」と言った。
以来、自分のひ弱さを見抜かれないために、自分自身が衣裳を纏って、素を隠した。常に黒いサングラスで目を隠し、現場ではキャップを被った。我ながら幼稚な発想に恥ずかしくもあったが、その姿で愛の前に立ったとき、彼女は声を出して笑いながらも「真面目な人ね。でも、スクリーンの世界は、それでいいのよ。あなたも役づくりしなきゃ」と言ってくれた。
周囲は何があったんだ、とさまざまに噂したが、何も語らず鬼となっていく咲島を感じ取るといつのまにか静かになった。マスコミに出るときは服装に合わせて帽子をいろいろと変える。映画賞の受賞式やパーティーではサングラスをはずすことなく、髪型をべたな七三分けにして出席し、とにかく変装をこころがける。そのせいか、無口にもなった。
ただ自宅以外の場所で唯一、ヒルトン東京では、柏原の前では、素顔の咲島で通せる。
また女性客の声がした。柏原の説明に応えたものだろう。
「そうするとウイスキーは、香りの花束なんですね」
女性客のひと言で、咲島の背筋に熱い電流が流れた。同時に真紅のバラに包まれた華杉愛の老いても美しい顔が映像となって浮かび上がってくる。
愛は咲島の弱さを鋭く突いた夜から3年ほどのち、休暇中の旅先で交通事故に遭い亡くなってしまう。身内の少なかった彼女のために、映画関係者が立派な葬儀を上げた。数えきれないほどの真紅のバラの花が愛の白く美しい顔を際立たせていた。棺からは愛の素晴らしい女優人生を物語るかのように麗しい香りが放たれていた。
長年、彼女を支えた女性マネージャーが、「愛ちゃん、香りの花束に包まれて天国に行くのね。最後まで、あなたは美しいまま」と言いながら泣き崩れた。
柏原がこちらにやってきたが、声をかけてこない。どうやら自分が難しい顔をして飲んでいるので気を遣っているのだと咲島は察して、話しかけた。
「外はとっても寒いんだろうな」
「雪になったと、スタッフからたったいま聞かされました」
柏原は生真面目に応える。
「そうか、やっぱり雪か。そういえば、愛さんは白い雪と赤いバラが似合ったね」
咲島がそう言うと、柏原は雪とバラがテーマになった愛のデビュー作のタイトルを口にした。
「淋しいだろう。愛さんという客がいなくなって」
「はい。でも、咲島さんが時折こうしていらしてくださいますので、時間が昔に戻るような、懐かしい思いに浸れます」
「きみは、愛さんに随分贔屓にされていたものな」
「咲島さんほどではありません」
「いやいや。わたしは監督なのに、大女優から説教ばかりされていたな」
咲島がこう言うと、柏原は「もう時効でしょう。ゆるしていただけると思いますので明かします」と真顔になった。
それは愛の若い頃の話だった。彼女は一度だけ結婚していたことがある。相手は男優で、数年で離婚している。その間、妊娠し、流産を経験した。
「誕生していたら、咲島さんと同い年だとおっしゃっていました。だからなのか、なんだか気にかかる。はじめてお仕事をされた時から、自分の子供と会っているような気持ちがつづいていると。女優としては失格だ、と。その夜は、普段よりもたくさんお召し上がりになっていらっしゃいました」
そう言うと柏原は口を閉じた。
おもむろにグラスの縁を口に当てると、バランタイン17年の甘美な香りが鼻腔をくすぐった。その香りはいつになく、目頭まで熱くくすぐった。
(第17回「香りの記憶」了)








*この物語は、実在するホテル、ホテルバーおよびバーテンダー以外の登場人物はすべて架空であり、フィクションです。
登場人物
咲島(映画監督)
 協力 ヒルトン東京
協力 ヒルトン東京